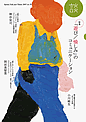| ![editor's note[before]](../../img/editor_before.gif)
遊びは文化に先行する
私たちは、いつ、どこで、どんな状態の時に「愉しい」と感じるのでしょうか。今号では、「愉しみ」について、主に「遊び」という観点から考えてみたいと思います。
遊び論の古典としてよく知られているものに、ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』があります。このタイトルにある「ルーデンス」とは、遊びという意味の形容詞ルーディック(ludic)からきていて、ホモが人という語ですから、これはまさしく「遊ぶ人」という意味です。オランダの文化史家で『中世の秋』の著作で知られるホイジンガは、人間は遊ぶ動物であるという意味を強調するために、自らをホモ・ルーデンスと呼びました。一般的に人間を表す言葉としては、ホモ・サピエンスあるいはホモ・ファーベルがよく知られています。サピエンス(sapient)が知恵のあるという意味であり、ファーベル(fabula)がつくるという意味のラテン語ですから、人間とは、知恵のある人であり、工作する人と定義されてきたわけです。しかし、ホイジンガは、この人間に関する従来の解釈を退けて、まず何よりもわれわれは遊ぶ人であり、遊びこそ人間にとって最も重要なものであると言ったのです。ホモ・ファーベルである前に、ホモ・ルーデンスである。別言すれば、文化よりも遊びの方が先行しているとホイジンガは大胆にも言ってのけたのです。 「自己完結性」としての遊び……ホイジンガの遊び論 これまでも、遊びについては哲学者や思想家、芸術家がたびたび言及してきました。そのほとんどは、遊びよりも文化が先行するというものでした。それに対してホイジンガは全く逆のことを主張したわけです。遊びこそ最初に存在し、その後にその他のもの、すなわち文化が追従して生じた。すべての文化に先んじる形で、遊びが存在していたというのです。
遊びの研究者であるM・J・エリス(後述)は、遊びの古典的、近代的理論をいくつか挙げています。たとえば、古典的理論としては、生存に必要とする以上の剰余エネルギーの存在によって引き起こされるとする「剰余エネルギー説」、生得的能力の遺伝によって遊びは引き起こされるとする「本能説」、元気を回復するために、労働でなされる反応とは別の反応を個人が必要とすることによって引き起こされる「気晴らし説」などがあります。また、遊びの近代理論としては、労働において報酬を受けてきた経験を遊びに用いるとする「般化説」、労働によっては満たされない、あるいは生み出せない心的欲求を満たすために遊びを利用するとする「代償説」、乱れた情動を、社会的に認められた活動に形を変えて、無害なやり方で表出しようとする「浄化説」等々。ホイジンガ自身も、著書の冒頭で従来の遊びの定義を列挙しています。遊びとは、「あり余る生命力の過剰を放出すること」であるとか、「先天的な模倣本能に従っている」とか、あるいは、「あることをしでかしてみたい」、「現実の中では満たされない願望をフィクションによって満足させたい」といったもので、エリスの挙げているものとかなり重複しています。
ホイジンガは、こうしてこれまでの遊びの定義を並べてみるとある共通点が見出せると言いました。いずれの理論や解釈も、「遊びは遊び以外の何ものかのために行われる、遊びとはある種の生物学的目的に役立っている」という前提から出発しているというのです。従来の、すなわちホイジンガ以前の遊びの理解では、遊びは、遊び以外の何かに貢献するために、さらには、遊んでいる本人が意識している/していないにかかわらず、常に同じような(生理的)反応として遊びは行われるものとみなされていた。そして、興味深いことに、エリスが列挙している遊びの理論にもそれは共通しているのです。
ホイジンガは、そもそもその前提条件がおかしいのだと言います。「遊びは、自発的な行為もしくは義務であって、それはあるきちんと決まった時間と場所の限界の中で、自ら進んで受け入れ、かつ絶対的に義務づけられて規則に従って遂行され、そのこと自体に目的をもち、緊張と歓喜の感情に満たされ、しかも〈ありきたりの生活〉とは〈違うものである〉という意識を伴っている」。
遊びは、遊び以外の何ものでもない。たとえば、遊びは緊張の弛みによる歓びだという考えがあります。しかし、ホイジンガは、逆に緊張がもたらす歓びもあるというのです。また、それは生理的な刺激反応の機械的な対応のようなものではなく、現に遊んでいる本人の意識が、遊びの面白さの程度に深く関わってくるようなものだというのです。遊びという概念は、「それ以外のあらゆる思考形式とは、常に無関係である。われわれは、幾つかの思考形式によって、精神生活や社会生活の構造を表現することができるが、遊びはそれらすべてにとって別のものなのである」。つまり、遊びとは、遊びそのものの中において完結する、そういう自己目的的(自己完結的)なものだというのがホイジンガの考えなのです。
遊びとは遊び以外の何ものでもなく、遊びそのものの中において完結するもの。そして、その遊びそのものの中に、緊張、歓び、面白さがある――。とりわけ重要なのは、この「面白さ」です。「面白さ」こそ、遊びの本質に他ならないとホイジンガは断言しました。
遊びの本質が「面白さ」であるとすれば、では、それはどのようなものでしょうか。ホイジンガの答えはこうです。それを問い始めると答えに窮してしまう。その答えられないということが、まさしく遊びというものの性質を如実に示していると。ホイジンガは続けます。「面白さ」とは何かと問う問い方そのものが遊びには向かないというのです。「遊びの面白さは、どんな分析も、どんな論理的解釈も受け入れない」ものであり、まさしくそのことにおいて遊びの本質が逆説的に示されているという。
遊びの本質が「面白さ」であることを示したという意味では、ホイジンガの功績は大きいとしても、その「面白さ」そのものの解明に至っていないというところに限界があるという指摘もあります。ともあれ、遊びを人の営みの中心に据えることで、新たな人間観を見出した意味は決して小さくなく、いずれにせよ遊びに関する考え、その枠組みを大胆に更新した功績は大きいと言わざるを得ません。 遊びを分類する……カイヨワの遊び論 遊び論において、『ホモ・ルーデンス』と並び称されるものに『遊びと人間』があります。著者であるロジェ・カイヨワは、ホイジンガの研究をベースにしながらも、ホイジンガが解明しえなかった「面白さ」の意味へ研究の触手を伸ばしていきました。
カイヨワの遊び論の功績は、大きく四つあります。小川純生氏(東洋大学経営学部教授)が、手際よくまとめているので、小川氏の議論に沿いながら紹介しましょう。その四つとは、一、遊びと文化の同時並行、二、「賭けと偶然」、「物まねと演技」の遊びへの付加、三、遊びの分類の試み、四、遊び概念による社会・文化の説明です。
一については、従来の考えを一八○度ひっくり返して、ホイジンガは、文化こそ遊びから生まれたと主張しましたが、カイヨワは、「遊びが文化から生まれる場合もあるし、文化が遊びから生まれる場合もあ」り、両者は相互補完的だと言いました。遊び、文化を明らかにするためには、ホイジンガ以前の文化先行型でみる見方もホイジンガの遊び先行型から見る見方も不十分で、両面からの考察が必要だというのです。遊びが先か文化が先か。簡単に言えば、「玉子が先か鶏が先か」と同じで、要するに両者は循環の関係になっていて、むしろ、両者を並列化させて捉える方がずっと生産的だというのがカイヨワの立場です。二は、ホイジンガが見過ごしていたもので、賭博やカジノ、競馬、富くじといった賭けごとを遊びの重要な要素として位置付けたことです。同様に、「物まねと演技」も、一種の虚構の活動であり、遊びのカテゴリーからは外せないものとして重要視しました。三の「遊びの分類」は、カイヨワの最も大きな貢献で、世の中に存在する遊びを全て(当時)一つの体系の中に組み込んで分類しました。四は、三の遊びの分類を基礎にして、西洋文明社会と未開社会の区別・違いを、計算の社会と渾沌の社会という切り口から説明したものです。カイヨワの遊び論でとくに重要なのは、三、四の遊びの分類とその分類を使って社会を見た文明論です。
カイヨワは、ホイジンガを参考にしながら、遊びを以下の六つから定義しました。1.自由な活動:遊戯者が強制されないこと。もし強制されれば、遊びはたちまち魅力的な愉快な楽しみという性質を失ってしまう。2.隔離された活動:あらかじめ決められた明確な空間の時間の範囲内に制限されていること。3.未確定の活動:ゲーム展開が決定されていたり、先に結果がわかっていたりしてはならない。創意の必要があるのだから、ある種の自由が必ず遊戯者の側に残されていなくてはならない。4.非生産的活動:財産も富も、いかなる種類の新要素もつくり出さないこと。5.規則(ルール)をもった活動:約束ごとに従う活動。この約束ごとは、通常法規を停止し、一時的に新しい法を確立する。そして、この法だけが通用する。6.虚構の活動:日常生活と対比した場合、二次的な現実、または明白に非現実的であるという特殊な意義をもっていること(『遊びと人間』四○ページ)。
これらの定義にしたがって、世の中の遊びを列挙し、独自の切り口から分類する方法を提起しました。いわば遊びの分類学とも言うべきものをカイヨワは試みたのです。それは次のようなものです。横軸に、計算/ルール/脱所属←→渾沌/脱ルール/脱自我、をとり、縦軸にパイディア(Paidia〈ギリシア語〉、遊戯/意志)←→ルドゥス(Ludus〈ラテン語〉、闘技、試合/脱意志)をとり、横軸と縦軸を交差させると四つの象限ができます。そして、そのそれぞれの象限に、アゴン(Agon ギリシア語 試合、競技)、アレア(Alea ラテン語 さいころ、賭け)、ミミクリ(Mimicry 英語 真似、擬態、模倣)、イリンクス(Ilinx ギリシア語 渦巻き)を配置したのです(図1)。そうすると全てとはいわないまでも、世の中のかなりの遊びが、この四つの象限に振り分けられることがわかったのです。たとえば、スポーツのほぼ全てがアゴンに、富くじ、カジノ、競馬はアレアに、カーニヴァル、演劇、映画はミミクリに、そして、眩暈をともなうもの、絶叫マシンやメリー・ゴー・ラウンドなどはイリンクスに分類されるというように。
さらにカイヨワは、この遊びの四つの象限を使用して、私たちの社会を計算の社会と渾沌の社会に分けることを行いました。計算の社会においては、アゴン(競争)とアレア(運)が、人間の技能と能力そして偶然、運を通じて、絶対的に公平な、数学的に平等な機会を求める重要な機能を果たすことになります。他方、渾沌の社会は、ミミクリ(模擬)とイリンクス(眩暈)、すなわち仮面と憑依が支配している社会です。ミミクリとイリンクスは、仮面と憑依を通じて、芸術、計算、巧妙、そして脱規則、陶酔と解放、混乱とパニック状態として、その社会を特徴付ける重要な役割を果たすというのです。
カイヨワは、「いわゆる文明への道とは、イリンクスとミミクリとの組み合わせの優位をすこしずつ除去し、代わってアゴン=アレアの対、すなわち競争と運の対を社会関係において上位に置くことである」と言い、未開から文明へと進歩する過程においては、社会におけるミミクリとイリンクスの要素を後退させ、アゴンとアレアの要素を優先させる必要があると結論付けました。 遊び論の拡張 ホイジンガが初めて明確な形で遊びを概念化させました。また、カイヨワは、その研究を受け継ぐ形で遊びに迫り、遊びを独創的な解読格子によって分類しました。遊び論におけるこの二人の功績は大変に大きいのですが、では、遊びの本質とは何かという問題になると、その核心にまでは迫りきれていないというのが一般的な評価のようです。ただ、この二人の遊び論を凌ぐような研究が出てきていないというのもまた事実であり、遊びの領域での新たな研究者の登場が待望されているというのが現状だろうと思われます。そうした状況の中で、遊びは遊びでしかないという認識に立ちながら、それを主体的な行為として、あるいは経験として捉えることによって、遊び論を更新しようという研究が出てきました。
M・J・エリスの「覚醒-追求としての遊び論」、M・チクセントミハイの「フロー体験としての遊び」、J・アンリオの「遊ぶ主体の現象学」、E・フィンクの「遊びの存在論」、竹田美喜夫氏の「疲労と倦怠の遊び論」などがそうです。彼らの研究は、いずれもホイジンガとカイヨワが放棄し、回避しようとした「遊び」の本質である「面白さ」に、あえて肉薄しようというところに、その特徴が見出せます。むろん、その試みが、すべて成功しているとは言い難いにしても、その姿勢は十分な評価に値するものだと思われます。彼らの研究の概要を紹介しておきましょう。
エリスは、活動水準を維持する働きを覚醒(arousal)という言葉で表し、この最適な覚醒水準をもたらしうる、もたらしそうな刺激は、個人にとっての「面白さ」を感じることができると言う。そして、遊びとは、「覚醒水準を最適状態に向けて高めようとする欲求によって動機付けられている行動」であると定義しました。最適覚醒の水準を維持させるためには、刺激を追求する場合もあれば、その逆に回避しようという場合もある。その統御の方法自体に遊びの面白さを見出そうとしたところに、エリスの遊び論の独自性があります。
チクセントミハイは、個人の楽しさ、喜びの経験を説明する概念としてフロー(flow)を提唱しました。フローとは、あるものごとに集中している時に、楽しさゆえにそれに完全にとらわれ、他のものごと、雑事、雑音、時間の経過を忘れさせるほどの状態をいいます。フローは、あるものごとに没入するという経験を通じて、「意味付け」と「楽しさ」を私たちに与えると主張しました。私たちは、遊んでいるそのまさに最中で何を感じているのか。その心的状態に内在的に迫ろうという挑戦的な研究です。
「すべては遊びであり、かつ何一つ遊びではない」。遊びとはプラクシスそのものであると喝破したアンリオも、遊びとは人間存在そのものであると主張するフィンクも、また、「遊びとは一切の有用性を超えた何かであり、その欲望、愉しみ、幸福は、絶対的に主体の側にのみ存する」と言う竹田美喜夫氏も、単なる文化史的、歴史的生産物としてではなく、内在的に「生きる」ものとして「遊び」と向き合おうとしている点では、同じ土俵に立っているといえます。とくに、これまでほとんど言及されることのなかった竹田氏の「遊びの身体現象」は、生-権力の健康支配から、徹底して逃走し続ける身体行為であり、疲労と倦怠それ自体を「遊び」と捉え直そうという他に類例を見ないアイデアです。「遊び」を受肉する身体と見るなどということが果たして可能なのか、竹田氏の研究は、「遊び」=「愉しさ」を身体の内側から捉える必要性を示唆しているようです。 今号では、「遊び/愉しみ」そして「遊び」について、三つの視点から掘り下げます。まず、ホイジンガ、カイヨワの遊び論・文化論、およびエリス、チクセントミハイの遊び=愉しみの現象論的分析に、消費行動論という視点から研究されている東洋大学経済学部教授・小川純生氏に、「面白い」とは何か、そもそもその根拠はどこにあるのか、お尋ねします。小川氏は、とくに、エリス、チクセントミハイの愉しみの議論について、情報との関わりから全く新しい読みを行っています。「遊び」はなぜ愉しいのか。いや、逆に愉しいという経験こそが「遊び」であるという、まさに「遊び」の本質に直結する議論を展開していただくことになります。
次に、近年再注目されている旧ソ連の心理学者ヴィゴツキーの遊び論を探ります。ヴィゴツキーの思想は、心理学の分野だけでなく、言語学、教育学、発達論、哲学といった隣接諸科学からも関心が高まっています。とりわけ、「発達の再近接領域」という概念は、独創的な発達論の地平を予期し、すでにそこにはシステム論的アプローチの萌芽さえ見ることができるというのです。そのヴィゴツキーには、これまでほとんど明らかにされてこなかった、もう一つの思想の流路が存在したのです。情動論です。情動論は、ヴィゴツキーにおける新たな鉱脈となりうるのでしょうか。保育という現場につきあいながら、遊びとの関連から、ヴィゴツキーの全体像に迫る研究をされている佛教大学社会福祉学部教授・神谷栄司氏に、ヴィゴツキーの遊び論、情動論についてお聞きします。
ロボティクスの分野でも、「遊び」が注目されています。それが、人間との共生を考えていくうえで、重要なコミュニケーションのインターフェイスになりうることが、近年の研究でわかってきたからです。ロボットと人間のコミュニケーションにとって、一見役に立たないように見えながら、じつはそのベースとなっているのが、ある種の「たわいのなさ」であることに気づいて、それを「役たたずロボティクス」と命名し研究しているのが、豊橋技術大学知識情報工学系教授・岡田美智男氏です。岡田氏に、「遊び/愉しさ」について、もう一つの鍵となる「コミュニケーション」について、おうかがいします。 (佐藤真)
|