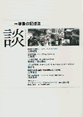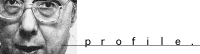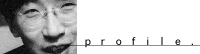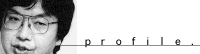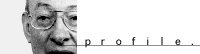| | 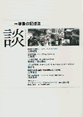 |
| 談 no.63 WEB版 | | |
| 特集:移動の記述法 |
| | Translated : Andrew Dewar
photo:鈴木理策(西部忠氏のみ西村陽一郎) |
| | | | |
| | 
|
移動する思考へ……レイブ・トランス・ディアスポラ
上野俊哉 Toshiya Ueno
ぼくはカルチュラル・スタディーズやポストコロニアル・スタディーズの主流――抑圧の構造を明確にすることで、国民国家と今の社会を批判するという態度――から、ちょっとズレているのかもしれません。いま、ここにある社会は、常にオルタナティヴなものを抱え込んでいる、それは未来にあるというのではなくて、まさに〈いま、ここ〉に潜在的な何かがあるということを示したい。繰り返しますが、日常の中に泡のように浮かぶ非日常ということですね。
-------------------------------
Toshiya Ueno's cultural studies sweep across structuralism, post-structuralism,
and even later thinking to create a new strategic theory. Most notably,
in recent years he has actively examined the subculture dance and
bodily entanglements at rave parties, to find a connection between
diaspora and nomadic thought. Taking the historical experience of
the Jewish Diaspora as a starting point, Ueno discusses the meaning
of travel, wandering, and the changes in body and awareness brought
about during raves.。
| うえの・としや
城県仙台市生まれ。
和光大学人文学部人間関係学科卒業、 中央大学大学院博士課程中退。 中部大学国際関係学部助教授を経て、 現在、和光大学人文学部文学部助教授。
著書に、『シチュアシオン――ポップの政治学』作品社、1996、 『人工自然論』頸草書房、1996、 『紅のメタルスーツ――アニメという戦場』紀伊国屋書店、1998、『ディアスポラの思考』筑摩書房、1999、
他がある。
|
|
| | 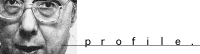
|
追憶の記述、ベンヤミンとパサージュ
三島憲一 Kenichi Mishima
ベンヤミンは『パサージュ論』の中で、一九世紀の資本主義の狂気の中で、人々が無意識に追求した夢を取り出そうとしたと言えるでしょう。エッフェル塔の背後にはどんな夢があったのか、と追求した場合に、利益や快楽の衝動や疎外、商品経済、物象化というところに結び付けるのは簡単ですが、そういうことを取り出す時に、そうした資本主義の集団的な無意識が最終的にどう変形してしまうかはわからない。だからこそ、ベンヤミンはいろんな側面から物事について考えるしかなかったのだと思います。
-------------------------------
The German-born Jewish philosopher Benjamin
had no hesitation about fleeing his country to avoid the
Nazis. But it was exactly this irresistible urge to flee
into self-exile that has driven his philosophy. His desire
to move himself eventually coalesced into a kind of strolling
philosophy. "Passage Theory," the huge collection of memoranda
that Benjamin has left us, is a record of urban landscapes
perceived by a moving eye and a strolling head. It is
also an archive of reminiscences. This paper examines
the stroller Benjamin's thought as a record of his movement. |
みしま・けんいち
1942年東京都生まれ。
東京大学大学院博士課程修了。 学習院大学文学部教授を経て、現在、大阪大学人間科学部教授。
主著に、『ベンヤミン』現代思想の冒険者たち09 講談社、1998、『ニーチェとその影』講談社学術文庫、1997、 『文化とレイシズ』岩波書店、1996、
『戦後ドイツ』岩波書店、1991、 他多数がある。 |
|
| | 
|
(対談) 桂 英史×渡辺保史
知の移動、バベルのネットワーク
ハッカーたちのつなぎたいという欲望がインターネツトをここまで大きくしてきたわけですから。それはTAやモデムにつなぐという物理的なことだけじゃなくて、論理的につなげるということです。それまで出会うことすらなかった風景や他者とつながっていく。これまでならナンセンスの一言で片付けられてしまったかもしれないこの「つながる」という感覚が正当性をもって実行されること。プロトコルを共有することによって、まったく見ず知らずの人と論理的につながるんです。(桂英史)
これまでインターネットを支えたのは、まさにそのアノニマスな、数多くのハッカーたちのアクティビティだった。アノニマスというのが今までのように「大衆」と一括りできるような、均質な集合ではない。それぞれの多様な知識や経験の断片をジグソーパズルのようにもち寄って、全体としては誰か特定の一人に帰着しえないような、思いもよらない成果を生み出す。(渡辺保史)
-------------------------------
"The dream of a library that contains every book and collects
all knowledge, is a dream that runs though the whole history of
Western civilization... This dream has also dictated an architecture
that strives toward the creation of a building that can hold all
of the world's memories." (Roger Chartier) Borges' library
of Babel was an expression of the desire to possess the world by
bringing together all of its countless books, and therefore all
knowledge within it. The explosive spread of the Internet has, however,
smashed Borges' dream of the collection and possession of knowledge
by making it seem merely megalomaniacal. Knowledge is no longer
something that can be possessed, but something that moves. All knowledge
is in a connective state. When a completely connected media environment
becomes possible, "knowledge" will become something completely
new, and all discussion of "knowledge" in an age of "IP
on everything" will revolve around the idea of movement!
|
かつら・えいじ
1959年長崎県生まれ。
図書館情報大学大学院修了。 富士ゼロックス情報システム、 ピッツバーグ大学客員研究員、 文部省・学術情報センター助手を 経て、現在、東京造形大学助教授。
著書に、『図書館建築の図像学』INAX、1994、 『インタラクティヴ・マインド』 岩波書店、1995、 『司馬遼太郎をなぜ読むか』
新書館、1999、 『東京ディズニーランドの神話学』青弓社、1999、他がある。
|
| | | 
| わたなべ・やすし
1965年北海道生まれ。
弘前大学人文学部卒業。 情報通信の専門紙記者を 経てフリーに。 フリーライター。
著書に、 『デジタルコンテンツの知的所有権』 オライリー・ジャパン発行、 オーム社発売、1998、 『グループウェアで会社を変える』
NTT出版、1998、 『はじめてナットク!マルチメディ』 講談社ブルーバックス、1995、 他がある。
|
|
| | 
|
LETSの可能性、グローバリゼーションへのカウンター・メディア
西部 忠
LETSは市場経済の中に微細な差異や多くの異物を差し挟んでいくことで、それらの存立構造の基盤そのものを揺るがし、グローバリゼーションという資本主義経済の原プログラムそのものを変容させてしまうような対抗「ガン」的運動になることができるのです。しかし、ただ単に資本の世界的な「移動」を行うグローバリズムに対抗するだけのものではありません。LETSはあらゆる意味での「移動」を可能にしています。たとえば、経済的な領域から文化的な領域へ、あるいは閉じた個や企業から、開いた多重人格的な個や企業への「移動」です。
-------------------------------
LETS is the acronym for the Local Exchange Trading System, a system
of local currency named by Michael Linton. Globalization has proceeded
rapidly in the post-Cold War global economy. The driving force behind
this trend is the possibility of capital investment free of the
restraints of national borders. But this sudden globalization also
carries the danger of national economies being torn apart. LETS
holds the potential for a completely new economic strategy that
resists the effects of globaliza tion and allows for local independence,
spontaneity, and autonomy. The basis of LETS theory as an alternative
economic strategy lies in the idea of autonomous control of movement
in an age of moving capital. The development of financial information
technology is actually pushing LETS forward. This essay examines
the increasing importance of movement in economics, and the possibilities
for alternative economies. |
にしべ・ただし
1962年福井県生まれ。
東京大学経済学研究科博士課程修了。
現在、北海道大学経済学部助教授。
著書・論文に『市場像の系譜学』東洋経済新報社、1996、 「<地域>通貨LETS 貨幣・信用を超えるメディア」 『可能なるコミュニズム』所収、太田出版、2000、
他がある。 |
|
| | 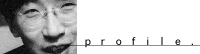
|
探索する身体、知覚−行為の経験としての移動
三嶋博之 Hiroyuki Mishima
知覚には終わりはないんですよ。視覚的な探索・移動は、毎日同じところを通っていても一回一回見ているところは違うんです。まったく同じところを通っているわけではない。同じところを通っていても靴の高さが変われば見ているものは違う。だけど同じところを通っているという感覚もあって、そこは非常に難しい。それをどうやって書くかですね。それをやろうとしているのがエコロジカルサイコロジーです。
-------------------------------
Ecological psychology takes an unprecedented approach to the relationship
between the actual act of sensation and environment. By introducing
the viewpoint of ecological psychology, which disputes many of the
basic tenets of traditional psychology, and by taking the paradigm
of sensory experience created by the assimilation of cross-species
sensory information, it is possible to allow "movement"
to become sensory behavior as a process of real activity. With the
ecological psychology espoused by James J.Gibson as a base, this
paper considers the methods of describing the movements of the body.
|
みしま・ひろゆき
1968年生まれ。
東京都生まれ。 早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。 現在、福井大学教育地域科学部助教授。
著書・論文に、「心理学の生態学的根拠」『間主観性の人間科学』所収、言叢社、1999、 「アフォーダンスとは何か」『アフォーダンス』所収、青土社、1997、
「運動制御への生態学的アプローチ」『運動』岩波講座認知科学第4巻、 所収、佐々木正人との共著、岩波書店、1994、 他がある。
|
|
| | 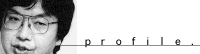
|
「変化」の記述法……メタモルフォーゼ、起滅、強度を手掛かりに
河本英夫 Hideo Kawamoto
言葉は言葉でネットワークをつくっていて、イメージはイメージでネットワークをつくっている。そこの間が何かでつながっている。この何かでつながっているという事態、異なるネットワーク間がつながっていることを、浸透(penetration)と呼んでいます。浸透という関係は、因果関係でもないし作用/反作用という関係でもないし、もちろん意味論的な関係でもありません。ただ、移動ということを考える時に最も重要なカテゴリーです。
-------------------------------
In the world of physics, attempts to define "movement"
are based on velocity, distance, space, and time. But the very words
used by natural science have deprived "movement" of its
true meaning. It is now necessary to reexamine "movement"
from a fresh viewpoint. Aiming at the world of life provides a way
into this new "science of movement." This paper considers
"movement" in the light of the new experiential sciences
of autopoiesis, Internal Measurement, and Affordance. |
かわもと・ひでお
1953年鳥取県生まれ。
東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。
現在、東洋大学文学部教授。
著書に、『オートポイエーシス2001』新曜社、2000、 『感覚』白菁社発行、ビー・エヌ・エヌ発売、1999、 『精神医学』共著、青土社、1998、
『オートポイエーシス』青土社、1995、 『自然の解釈学ーーゲーテ自然学再考』海鳴社、1994、 『諸科学の解体ーー科学論の可能性』三嶺書房、1987、
他がある。 |
|
| | 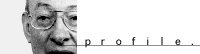
|
快楽の効用……楽しみの起源から探る
デイビッド・M・ウォーバートン David.M.Warburton
ARISEの一つの目的は、世界では人々がさまざまな快楽活動をしているということ、それが世界で普遍的であるということ、その楽しみというものは私たちにとって自然な人間の感情状態であって、私たちのからだであるとか脳も楽しみを得ようとしている存在だということに注目し、そのことを広く世間に提示していくことです。
-------------------------------
We humans have chosen many pleasure-oriented behaviors during
our evolution. Pleasure has been a very import element of that
evolution. ARISE (Associates for Research Into the Science of
Enjoyment) has, in numerous studies and fieldwork reports, studied
the relationship between our uses of pleasure and our culture.
David M.Warbuton, who came to Japan for the ARISE International
Symposium, discusses pleasure and the sources of delight. David.M.Warburton
|
David.M.Warburton
1938年生まれ。
ロンドン大学で博士号取得。 インディアナ大学で博士号取得。 カリフォルニア大学アーヴィン校勤務を経て、 イギリス・レディング大学勤務。
1980年に行動の生化学に関する研究で、 パーソナル・プロフェッサーに任命される。 現在、レディング大学教授。 人間精神薬理学グループ所長、ARISE会長。
|
| | | 
| [聞き手] すずき・たかし
1961年東京都生まれ。
早稲田大学第一文学部 フランス文学専攻卒業。 現在、高砂香料工業株式会社 フレグランス研究所勤務。 著書に、 『匂いの身体論』八坂書房、 1998がある。
|
|
| | | ![editor's note[before]](images/editor_before.gif)
移動論は何を問題にするのか
差異、移動の発端
いったいモノが移動することと情報( コト)が移動することでは、何が違うのだろうか。私たちは、今それを正確に言いあてることができなくなっている。そこにさらにヒトを付け加えてもいい。ヒトが移動することもまた、モノやコトの移動と大きな差がなくなりつつある。ヒト、コト、モノが複雑に絡み合いながら移動する、私たちは、そういう時代に生きている。
二○世紀末は、人類にとって移動が最も広範囲にまた大規模に起こった時代だといわれている。地球上のあらゆる地域を、さまざまな移動手段を利用しながら、日々人々は駆け回っているからだ。自らの意志で、目的を遂行するために外へと出ていく人間たち。彼らにとって、移動することは生きることの証明でもある。国境は彼らにとっては、生の飛躍のためのほんの小さなハードルにすぎない。
しかし、一方で、移動が生存のための条件になっている人間たちもいる。留まることが許されず、無理やりに追いたてられて、外へと向かわざるをえない人々。難民と呼ばれる現代のディアスポラたちにとって、国境は死と生を分ける踏み絵である。国境を越えることは、すなわち故郷の喪失、記憶の忘却を意味する。だが、彼らにそれ以外の選択肢は与えられていない。移動は、彼らにとって文字どおり命がけの飛躍でありかつ唯一の選択肢であるのだ。進んで移動する者と移動を強いられる者。ボーダレスという言葉は、両者ではまったく異なった意味をもつ。
二○世紀の最後の十数年間は確かに移動の世紀であった。だが、二○世紀全般で見ればむしろ移動が厳しく制限された時代だったとみる方が正しいだろう。二つの大戦を挟んで、国家(ネーション・ステート)がその支配力を強化することによって、必然的に国境は固定化していった。それが多分に地勢学的な線引きであったとはいえ、いったん引かれた国境を自由に往来することは困難だ。一時的にせよ(しかし、それは五○年以上続いた)、国家が人々の移動を拒んだのである。
そうしたかりそめの安定状態が崩壊し、再び人々の移動が活発化したきっかけは、いうまでもなく冷戦体制の崩壊である。世界が一挙に巨大な単一の市場へと変貌し、民族問題が噴出した九○年代。いわゆる経済のグローバル化、さらにはナショナリズム・レイシズムが加わって、再び人口の流動化を促し、地球規模の移動へと人々を巻き込んでいった。
世界が市場経済(資本主義)の波に飲み込まれていく時、人間はどのように行動するのだろうか。たとえば、労働者は、より高い賃金を保証してくれる場所を求めて移動する。一方、労働市場全体は、より安価な労働力が提供される場所へシフトする。そこにあるのは、きわめて単純な論理だ。とはいえ、この構図がいかに正鵠を射たものであるかは、ベルリンの壁崩壊後の東ヨーロッパ、あるいは八五年以降の東アジア圏の人口動態を見るだけで明らかであろう。また、どこに資本がより多く投下されるかについても同じ論理が働く。より収益の上がる場所により大量に資本は移動する(投下される)。資本主義における経済活動は、バカ正直なまでにこれまでの慣例を反復し続けるのである。
動機や要請が異なっていても、移動の様態には共通性が見いだせる。移動の発生は、差異が引き金になっていることだ。差異があるところに移動が生まれる。賃金の格差であったり、労働環境であったり、また自由があるかどうかというのも差異である。差異の中身は多種多様だ。距離それ事体が差異となりうることもある。「ここではないあそこ」「あそこよりここ」というだけで、ヒトは移動することさえある。フロンティアを求めて移動する者、故郷を追われる者、あるいは移民、難民、亡命者、漂流者……、出自も歴史も目的も違う人々が移動し、あるいは移動させられる時、そこには決まって差異がある。
今号は、移動がテーマである。もとより、ヒトだけが移動するわけではない。冒頭で言ったようにモノやコトも移動する。そして、移動の発端には必ずといっていいほど差異があるのだ。いきなり結論めいたことを言ってしまおう。差異とは何か。その正体をつかむことができれば、移動というものが理解できるはずである。私たちは移動という様態を把握するために、差異が発生するさまざまな場所に思考を巡らせてみたい。
移動論の射程、「旅する身体」
「旅」が移動論という姿をとって活発に議論されたことがあった。 「旅の本質は物質的な移動だ。大きな犠牲を払い多くの荷を担い長い時間を費やして、はじめて眼にし肌をふれすべての感覚をみたすことのできる地平は、無限に存在する」(『トロピカル・ゴシップ』管啓次郎)
サンパウロ、タヒチ、アリゾナ、ハワイ、シアトルと自ら移り住みながら、旅の思考を深めていった著者によれば、移動によって明らかになったことは、何よりもヒトというものが本源的に混血であるということだった。たとえばブラジル人の美しさは、血統も遺産も受け継ぐことなく定住さえしないで移動してきた者たちによってつくり出された混血性の証である。虹色の連続体としての肌の色のあいまいさは、生きる原理としての混血性を明らかにするという。
混血としてのヒト。いやもっと正確にいえば、混血であることを希求したヒト。人類にとって、混ざり合うことは必然であった。クレオール、あるいはクレオール文化論は、そうした混血性の優位を高らかに宣言したものであった。「旅」がクレオールと接続するのは、この両者の根底に同居するヒトの移動性においてである。
「旅」することによって、純潔性の神話はいとも簡単に暴かれる。地球上のほとんどは、混血地帯だからである。混血性としてのヒトという自明であるがゆえに隠蔽されてきたヒトの本性は、「旅」をすることによって明確に自覚されることになる。そしてその自覚は、やがて自らもそうした混血の系譜を受け継ぐ者であるという確信へと導かれるであろう。日本人=単一民族説の嘘が、あからさまになるからだ。よく知られているように、一万年前には、日本はユーラシア大陸の一部であり、ベーリング海峡、マラッカ海峡、アリューシャン列島は陸続きであった。現在のエジプトからアラスカまで陸伝いに移動が可能だったということだ。もっとも、新しい学説によれば、アリューシャン列島からアラスカ南岸への太平洋ルートによって、人類はポリネシアからアメリカ大陸へ渡っていたのではないかという報告もある(サンパウロ大学の人類学者ウォルター・ネヴェスの説)。つまりアメリカ人の祖先はモンゴロイドであるという定説に疑問を投げかけたのである。そうなると縄文人と最初のアメリカ人は親戚ということになる。もはや、混血でない民族を探し出す方が難しいということなのだろう。
「旅」がそうした人類の混血の歴史に重ね合わされる時、人間のクレオール性が浮上する。クレオール文化論は、だから最初から移動の文化を射程にしていたのである。身体の移動という具体性の中で自らの混血性に遭遇する。クレオール文化論は、ヒトが混血性と文化融合の容器として存在することだというだけではなく、移動する身体であることを明らかにしたのである。
「旅は撹拌する溶液に似ている。溶液、半凝固体、個体、粒子といったさまざまにことなる形態を持った物質が、勢いよくまぜあわされて色や濃度や比重を変えてゆくさまは、ちょうど旅の移動のさなかに変容するリアリティの感覚を思わせる」(『移動溶液』今福龍太)
今福龍太氏にとって、まさに旅とはそうしたヒトのクレオール性に目覚め、また自らがクレオール化していく過程として捉えられている。つまり「旅」とは、この撹拌の力が、ヒトの身体に注入されることだというわけだ。その時「旅する身体」は、どこかに向かって溶け出し、自己の存在の様態さえも以前とは違ったものに変わってしまうかもしれない。しかし、それこそがまさしく「旅」の、つまり「移動」の核心的意味だというのである。
年間一六○○万人もの日本人が海外に出るという。その多くは観光客である。いまや、日本人にとって外へ出る目的は、外を見ること、観光行為に置かれている。半世紀前の日本では、海外に出る者のほとんどが軍人であった。その様変わりぶりは、日本人の移動のイメージを覆して余りあるものだろう。観光客として海外へ出ていくことが、私たちにとっての「旅」であり、移動だといってもいいのである。今後観光が、私たち日本人にとって、気晴らし以上の意味をもつものに成長する可能性はないとはいえない。仮に観光が日常化し常態化するような時には、われわれ日本人の生活様式が移動によって規定されることもありうるだろう。「旅」をそのように日常性のうちに埋め込んでいくことによって、われわれの身体は、移動する身体として新たなリアリティを発見するはずだ。移動する身体、繰り返すまでもなくそれは絶えざる変容のプロセスなのだ。
非日常のイベントとしてではなく日常性として「旅」を自覚する時、観光客は旅行者に変わる。観光客は旅行という時間を空間の移動として認識する。だが、旅行者は空間の移動を時間の移動として認識する。この二つの認識は、移動にかかわる本質的な意味の違いを表している。観光客は、自らの文化コードを捨てることなく、それをまとったまま移動するのに対して、旅行者とは移動先の文化コードを自らに取り込んでいく。観光客における移動は、ホリゾンタル(水平的)な移動である。ところが、旅行者の移動はバーチカル(垂直的)な移動である。旅行者はもはや移動そのものを生きるのである。
旅行者の自覚するこのバーチカルな移動の様態。意識変容へと至ることさえあるこの移動の身体性について、私たちは、まず移動についての最初の考察を、ここから始めることにしよう。
クレオール文化論からカルチュラル・スタディーズヘ
クレオール性としての身体の出会いが、ポストコロニアル状況への分析、コミットメントへと深化していく時、クレオール文化論の政治学としての側面が一気に前景化する。それはそのまま九○年代以降の、カルチュラル・スタディーズへと引き継がれていくことになる。ポストコロニアル状況とは、狭義には支配/従属という国家的制度的枠組みが解体した以後の旧植民地地域の文化状況を総称するものだが、旧支配国の文化状況をも巻き込んで展開する重層的な現代の文化全般を意味するものとして捉えていくと、私たちの生きる世界そのものがその対象領域となる。ポストコロニアル状況はその意味で私たち日本人にとってはとなりの芝生であるどころか、まさしくわが庭の問題として捉えられるべきものである。
ポストコロニアル状況をわれわれの文化的なコンテキストとして対象化しながら、その読解を通して文化研究・文化批評へと展開していったのがカルチュラル・スタディーズである。カルチュラル・スタディーズを直訳すれば「文化研究」で、それを字義どおりに受け取って、日本ではサブカルチャーに代表されるようなポピュラー文化の実証的な研究というような理解のされ方で受容されたところがあった。しかし、本来ポストコロニアルな日常文化全般への実証的経験的研究という面を正確に把握するならば、それが単なる誤読だということはわかるだろう。クレオール文化論と共振しつつ、その問題意識を政治的な領域へと押し広げていったものがカルチュラル・スタディーズである。そうした側面を正当に評価すれば、身体の理論としての可能性も開けてくる。
クレオール性は政治的空間に配置された身体の様態である。言い換えれば、身体が文化様式を織り上げられていく過程で表象するものがクレオール性なのだ。だとすれば、その身体の様態とは何か。ポストコロニアル状況において、そうした様態へと変容する身体とはどのようなものか。
カルチュラル・スタディーズの研究者が一様に「移動」に照準を合わせるのは、ポストコロニアル状況において身体の変容、様態の変換が「移動」という契機を介して起こるからである。二○世紀の文化そのものが常に「移動」によって成立していたという歴史を踏まえたうえで、「移動」という形態が与えた痕跡としてポストコロニアルを考えていくこと。集団的記憶やその忘却、あるいは想起、さらには無意識がポストコロニアルという政治的空間上にどのように備給されるのか、カルチュラル・スタディーズは人々の「移動」の経路、交錯から探査するという方法で検証しようというのである。しかも興味深いことは、彼ら自身自らを移動する者として規定していることだ。自らの思想を「旅する理論」と呼ぶエドワード・サイードの言葉を借りれば、さまざまなフィールドへ出向き、さまざまな人間と接触・交流すること、「移動」によって思想を形づけていく姿勢そのものがカルチュラル・スタディーズの研究態度だといえる。
ポストコロニアル状況における文化・身体の複雑な関係を「移動」を手掛かりに解読するカルチュラル・スタディーズの方法を探ってみよう。お尋ねするのは、和光大学人文学部文学科助教授・上野俊哉氏。上野氏は、カルチュラル・スタディーズにかかわり、それを構造主義、ポスト構造主義以降の思想と横断させることによって新たな戦略理論として練り上げていく作業を続けておられる。とくに近年では、サブカルチャー・ダンス・身体が交錯するレイヴ・パーティに積極的にかかわりながら、ディアスポラ(離散)をノマド・「移動」の思考との接点で考察している。上野氏に、著書で言及されているユダヤ人たちの歴史的体験に根ざしたディアスポラという概念を手掛かりに、移動の形態としての旅、漂流、また身体や意識の変容の場としてのレイヴの意味についてお聞きする。
パサージュ、インターネット、グローバリズム
「場の移動を余儀なくされる主体は労働の現場のみならず、資本を再生産するための流通と消費の網の目においては、まさに街路の迷宮をほっつき歩く遊歩者として現れる」「〈遊歩者〉stroller、言うまでもなくこれはボードレール/ベンヤミンによる都市の分析の主体である」(『ディアスポラの思考』)
上野俊哉氏は、ディアスポラが移動の起源へのノスタルジーよりも、その「効果」の方に向かうための戦略であるとして、ディアスポラと遊歩者を接木させるという刺激に満ちた議論を展開しているが、その遊歩者という概念を提起したのは、いうまでもなくヴァルター・ベンヤミンであった。
ドイツ青年運動、 マルセル・プルースト、シュルレアリスム、マルクス主義、ユダヤ神秘主義を吸収しつつ、徹底してラディカリストであり続けようとしたベンヤミン。一九四○年スペインで自ら命を断つまで、二○〜三○年代のベルリン、パリという二○世紀都市文化の醸成地を往復し、多岐にわたる著作を残したベンヤミンは、また「移動」を批評言語へと昇華することを試みた思想家でもあった。彼にあっては、「移動」することが思考であり、思考することが「移動」であった。通称『パサージュ論』と呼ばれる膨大なメモは、ベンヤミン自らの記述とさまざまな引用のアマルガムによる集積である。
パサージュとは、英語でいうアーケードのこと。つまり商店街にあるあの屋根のかかった通路のことだ。だが、もとよりベンヤミンはそうした狭い意味としてだけではなく、通路、通行、変化、走狗といった多義的な意味をもつ概念として「パサージュ」という言葉を使用した。要するに、何かと何かが交通する場(「ベンヤミンを挿入し、ビルディングタイプの壁を破壊せよ!」五十嵐太郎)がベンヤミンにとってのパサージュであった。
「パサージュ論」の全体像は、まさに「移動」と「思考」が一体化した一個の巨大な星雲であったといっていいだろう。私たちは、次にこのベンヤミンの残した「移動」の記述、パサージュ論に言及してみたい。
「遊歩者の歩くパリは世界都市である。つまりその通りの名前にフランスの各地方を人口や地勢に応じて割り当て、それによってパリがフランスの縮図になり、フランスがパリの拡大図になるような都市であり、街路名によって〈言葉の宇宙〉となるような世界都市である。室内も風景も世界都市としての性格を持っている。あるいは世界のバロック的迷宮性が現れている」(『ベンヤミン』三島憲一)
ベンヤミンの「移動」の思考は、具体的な「パサージュ」へと逗留されることによって、明確な都市の理論へと発酵していった。パリがバロック的な迷宮としてその姿を現す瞬間、それを感受できるのは遊歩者である。ベンヤミンにあって「パサージュ」とは「交通」が激しく起こるバロック的な場であり、それを感受する遊歩者もまた交通するヒト、バロック的な人間である。ここでいうバロック的とは、ライプニッツのいうモナドのことだ。至るところ穴だらけでありながら、しかも閉じている場。交通とは、こうしたモナドのような場で起こる相互浸透的な状態のことをいう。この相互浸透的な状態をいかにして記述しうるか。ベンヤミンのパサージュ論の膨大なメモは、まさにその試みへのエスキースであった。「移動」しつつ記述するというのではなく、「移動」を記述すること。ベンヤミンの無謀ともいえるこの企てについて、大阪大学人間科学部教授・三島憲一氏にお尋ねする。
ベンヤミンがパサージュに見たモナドとしての交通の場を、現代の交通空間に置き換えるとどこに見いだすことができるだろうか。現在残っているパリのパサージュは、ベンヤミンのパサージュとは似ても似つかない代物である。もはやパリのパサージュは、単なる懐古的雰囲気を醸し出すだけの街路にすぎない。むしろ二○年代のパリのパサージュ空間と同質のものは、現在のWWW(ワールド・ワイド・ウェブ)にこそ出現していると考えるべきではないだろうか。ベンヤミンがもし今生きていたら、まちがいなくインターネットのウェブがそうした交通の場であると言ったに違いない。デジタルかそうでないかという違いはもはや問題ではない。インターネットこそ、今日では交通空間の最もポピュラーなモデルだと考えていいのである。
そこで改めて次のように問うてみたい。インターネットが現代の交通空間を表象するものであるとして、ではそこで移動しているものとは何か。いったいインターネットという空間で何が交通しているのだろうか。私たちが問題にする移動論は、この問いを前にして大きく旋回することになるだろう。移動をどのように記述するか、私たちが問題にしたいのは、まさしくその記述の仕方なのである。
その前にひとまずインターネットという現代の交通空間について見ておこう。とくに移動という視点から、それをどう理解していくか考えてみよう。ここでは二人のプロパー、東京造形大学助教授でメディア論を専攻する桂英史氏とフリーランス・ライターでデジタル・メディアを研究する渡辺保史氏に議論していただく。
さて、記述の問題に入る前にもう一つデジタル・ネットワークに関連して、グローバリゼーションに触れておきたい。冷戦後の九○年代において世界経済は大きな変動を経験している。その最大要因がグローバル経済の進展である。自由投資市場という枠組みの中で資本の移動が加速度的に進行し、そこで発生する差異が膨大な富と経済危機を生み出す。世界経済はいわゆるカジノ経済と化し、金融システムの危機がいつ起こっても不思議でないような不安定な状況が続いている。かつて共産主義がそう喩えられたと同じ理由で、グローバリゼーションとは一種の妖怪だといえる。こうしたグローバリゼーションは、繰り返すまでもなく地球規模で起こる資本の自由な「移動」を要件としているのだ。差異の関係によってヒト・モノ・コトの移動が起こる。一つの国民国家が一夜にして壊滅することもありえるグローバリゼーションの波は、どんな小さな差異も見のがすことがない。このように不安定な世界経済が自律性を保ち続けるということが果たして可能なのだろうか。あるいはグローバリゼーションに拮抗しうるような新たな経済システムが構築できるのだろうか。
お尋ねするのは、北海道大学経済学部助教授・西部忠氏。私たちのこの質問に対して、西部氏はグローバリゼーションに対抗するシステムは存在し、それはLETSというまったく新しい地域通貨であるという。そして、LETSが対抗勢力となりうるのは、それがまさに「移動」することを条件とするようなシステムだからだというのである。
行為を記述する、変化を記述する
「移動」に関して、とりわけ身体行為としての「移動」に関する観察・分析は、従来実験系の心理学が扱ってきた問題である。行為、動き、運動をどのように捉え記述するか、それは心理学においても容易なことではなかったようだ。たとえば、認知心理学では統合化された知覚運動システムとしてそれを捉えたうえで、そのシステムのメカニズムを解析することによって、それを記述していこうとした。だが、この試みはその端緒においてアポリア(困難)を導き入れてしまう。アプリオリに知覚と運動を知覚されるものとしての外界と分けるところから出発し、そのインタラクション(刺激→受容→情報処理→反応)として知覚と運動をつかまえようとすることからその困難は生じる。情報処理機能の分析に関しては、コンピューティングの技術の飛躍的発達も手伝って洗練さをきわめているが、S-R機構を温存しているという意味では旧来の身体観を踏襲するものである。神経生理学の成果および脳の最新研究を総動員して取り組んでいるものの、いわゆる心身二元論による身体図式を抜けきれていない以上、そこには限界がつきまとうだろう。知覚と運動の機構を、まず従来のフォーマットから解放させることが先決である。
「すべての行為……有機体の形態形成も含めて……は、その行為が行われる環境なしには成立しない。行為の実現において、生物と環境の両方が立ち会っており、両者は対等である。これはおそらくジェームス・ギブソンがもっとも強調した点である」(「知覚-行為循環 有機体と環境、情報と力を持続する場としての」三嶋博之)
ギブソンは、アフォーダンス理論を提唱した心理学者である。『談』ではこれまで何度かアフォーダンス理論を紹介してきたが、実はアフォーダンスは、まさにその旧来のフォーマットへの批判として提起された理論であった。知覚の問題を研究するためには、動物と環境の相互性が強調されなければならない。
福井大学教育地域科学部助教授・三嶋博之氏は、アフォーダンス理論の根拠となる「生態心理学」に準拠して、行為と環境のかかわりからなる知覚の理論化に取り組んでいる。知覚は人間にだけ特有のものではまったくない。動物進化のプロセスで形成されてきたメカニズムである。そこで重要になるのは、動物の環境への探索であり、探索とは「移動」の一つのあり方であるという。「生態心理学」は、「移動」を動物のリアルな運動のプロセスとして記述しようとしている。そこで、三嶋氏に身体の行為としての「移動」について、それをありのままにつかまえる方法をおうかがいする。
さて、「移動」をありのままにつかまえる手っ取り早いやり方は、自らが「移動」することである。ベンヤミンが企てたような、移動することが思考することになるような方法をつくり上げる必要がある。それは心理学、哲学、社会学といった個別の分野の問題としてではなくて、経験科学一般の問題として捉え直されなければならない。
「〈…〉まるで静止した映画の一コマ一コマを配列したようになる。そこで時間点の間隔を短くし、静止していると感じられないほど状態記述を立て続けに配置することになる。このとき観察者からみれば、その対象は動き続けているように見える。しかしかりに人間の細胞の状態を一瞬一瞬で静止させて記述し、それを緊密に配列した場合、それで動き続けている細胞を記述したことになるのだろうか」(『オートポイエーシス 第三世代システム』河本英夫)
答えはもちろんNOである。何が違うのだろうか。アニメーションと違い、細胞は自分自身で動き続けている。観察者が見ようが見まいがそんなことはお構いなく、ただ動いている。勝手に動き続けているだけなのだ。それを記述するには、観察をするだけでは不十分であり、むしろ動き続けることそのものに身をまかせる必要がある。それは「行為」することにほかならない。日々変化し、差異化しているという「行為」それ事態を捉える方法を生み出さなければならない。従来のとはまったく異なる新たな経験科学の方法が獲得されなければならないだろう。
東洋大学文学部教授・河本英夫氏は、そのアプローチの有力な概念装置としてオートポイエーシスの理論化に尽くしてきた。ポイエーシスとは、制作行為のことであり、アリストテレスは理論と実践に対峙するものとしてポイエーシスという概念を提唱した。行為の継続が自己そのものを創発すること、オートポイエーシスとは自らが変化していくことだ。河本氏に、オートポイエーシスの考え方を導入することによる「移動」の記述法について考察していただく。
「移動」、それは自らが自らを「差異」化していく行為なのではないか。その問いと共に自らの「旅」を始めることにしよう。
| |
| |
| ![editor's note[after]](images/editor_after.gif)
「移動」、常に生まれ変わり、
あらゆる場所に同時にいる「私」
〈いま、ここ〉をトランスしたい
インタビューと対談の内容を振り返りながら、「移動」についての議論を深めていこう。 「ディアスポラという言葉と概念を、一見それとは無関係に見える日常生活や生活世界全般における文化的/社会的要素としての移動、漂流、流動のダイナミズムの中に透かし見ることによって、(…)つねにすでに根源的な移動に巻き込まれている思考、あるいはそうした身ぶりとしてうきぼりにしようと試みた」(『ディアスポラの思考』)
上野俊哉氏が、自著でこのように語る時、カルチュラル・スタディーズとのかかわりは彼にとって相対的なものだということがわかるだろう。ディアスポラを現代の資本主義への抵抗のための戦略として位置づけ、それをポスト構造主義、とりわけノマドの概念との連関で論じるポール・ギルロイへの共感や言及も、カルチュラル・スタディーズという学問動向への関心というよりは、純粋に思想的な動機から生まれたもののように思われる。したがって、カルチュラル・スタディーズのスポークスマンでもなければ、その研究姿勢に対する強い思い入れももっていないと上野氏が強調するのは、ある意味では当然のことなのである。それどころか、カルチュラル・スタディーズがアカデミズムのフロンティアとして大学の内部に制度化されることには懐疑的な態度を崩していない。上野氏がカルチュラル・スタディーズを評価するのは、それが現場的なという意味で、また「新しい社会運動」として機能するという意味で、役に立つ道具になりうると考えるからである。日常生活の分析と批判のための道具としてカルチュラル・スタディーズとかかわり続けたいという上野氏の姿勢は、だからきわめて自然なものなのだ。カルチュラル・スタディーズに対しては批判も少なくないが、上野氏は、あくまでもそれを実践的な側面で受け止めている。そうした立場を認識したうえで、上野氏の発言を整理してみよう。
上野氏は、日常生活の中に溶け込んでしまっている、さまざまな言葉にならない事象をすくい出し言語化しようとするところにカルチュラル・スタディーズの有効性を見いだす。たとえば、日常性としてある階級の問題を性差や民族と結び付けて考えようとしていることや、ストリート・カルチャーや若者の現場と密接につながっていることが、カルチュラル・スタディーズの重要なポイントだと見る。それはまた、日常生活の中に潜む新たな論理や思想の種を取り出していくことにもつながっていく。
上野氏は、一方でポスト構造主義の中で培われてきたノマドの思考を突き詰めていく過程で、それを単なる移動の文化論として楽観的に肯定する態度を批判しながら、歴史的思想史的事実としてのディアスポラと接合することによる「移動の思考」を模索する。カルチュラル・スタティーズは、ポストコロニアル状況下における追放、亡命、漂流といった故郷喪失の体験を問題にしてきたが、上野氏はその問題意識を自らの「移動の思考」へと呼び込み、独自の「旅の理論」へ練り上げようと試みている。その過程で上野氏は、レイヴに出会う。レイヴは〈私〉・個を雲散霧消させ、トライブを意識させ、さらには、〈いま、ここ〉からのトランスへ自らを導く。trance
でありtransであるという経験。ハキム・ベイの言うテンポラリー・オートノマス・ゾーンを、そうしたトランスの経験の場として読み替えていく時、それは新たな「旅」・「移動」の理論となる。「移動」とは、日常と非日常の境界それ自体を押し広げていくトランスとしての運動であるという。
上野氏が言うトランスの感覚は、ドゥルーズの強度(インテンション)の概念ときわめて近いもののように思える。また、カルチュラル・スタティーズの論客の一人ローレンス・グロスバーグがやはりドゥルーズ・ガタリから援用した情動(アフェクティヴ)という概念とも共振する。移動が常に空間として意識される中で、強度や情動と重なり合うトランスという概念は、時間性を強く意識させるところが興味深い。空間の移動が時間の意識を突き動かすのである。
〈いま、ここ〉という一瞬間、あるいは陶酔するという感覚。時間の側から見れば、そうした感覚が引き起こすものは、おそらく「時間の消滅」であろう。一瞬であると同時に永遠であるような時間の感覚。空間をトランスバーサルする身体が感じるこの「時間の消滅」という感覚は、「移動」の身体性を考える場合、重要な意味をもつ。editor's
note beforeで「旅」に触れて述べたように、たとえば、旅行者にとって移動が本質的にバーチカルなも のとして認識されている場合は、それは単に空間上の移動を意味するだけではない。それは時間の移動でもある。水平面上の移動が垂直軸上の移動と重なり合うような経験、それは移動そのものを生きることにつながっていくからだ。移動する身体に埋め込まれているものは、こうした「時間の消滅」の感覚ではなかろうか。それは、時に物理的な移動なしの移動の感覚を身体にもたらす。それがドラッグの体験であることはいうまでもない。じつはレイブとドラッグ体験は深いつながりをもつ。トランスを問題にする時に、ドラッグを無視して論じることはできない。このことはいずれきちんと議論しなければならない問題だが、ともかく、ここでは移動がもたらす感覚として「時間の消滅」があることを確認しておこう。
コンステレーションを読み解く
ベンヤミンは、日本では当初マルキストとしての側面が強く打ち出されていた。従来のマルクス主義者に抱いていたイメージとはかなりかけ離れていたものの、いったんそうしたコンテキストの中に押し込められてしまうと、どうしてもその評価は一面的にならざるをえない。さらに多岐にわたる評論活動がかえって災いして、思想の全体像も一貫性を欠くものとみなされてきたようだ。ベンヤミンは二○世紀を代表する思想家といわれながらも、その評価となると相当にばらばらであったといえる。
ところが、ベンヤミンの思想的遍歴の中で、マルクス主義、プルースト、シュルレアリスムのほかに、ゲルハルト・ショーレムを通じて出会ったユダヤ神秘主義が、じつは彼の思想に決定的な影響を残していることが次第に明らかになって、ベンヤミンの評価は大きく変わった。むろん、マルキストとしての側面を無視するわけにはいかないが、一貫性を欠くようにも見えたその思想が、ある方法論にもとづくものだということが明らかになってきたのだ。コンステレーションがそれで、無意志的記憶、自然の解放、そして遊歩という発想にもその考えは深く入り込んでいる。ここで取り上げた『パサージュ論』は、コンステレーションとの関連で読み直してみることによって、その意図がより明確な輪郭を伴って現れてくる。三島憲一氏のインタビューを要約してみよう。
「ベンヤミンの中に現実でないものに憧れた一九世紀の夢と、それらを思い起こす追憶の夢という、二つの夢が同居していたと考えられる。一九世紀のカフェやバー、劇場、商店を並べてみた時に、そこに見えてくる一つのイメージがある。それは夜空の星の配列とも似た、いわば無意識がそのまま現出しているイメージである。決して隠されることなく表層に表れているもので、ある関連性をもつもの、それをベンヤミンはコンステレーションと呼んだ。パサージュも近代化の産物であり、近代が生んだ夢の形象である。パサージュはその意味で資本主義が覆い隠してしまった一九世紀の夢が並ぶ、いわば記憶のコンステレーションだとベンヤミンは考えた。
ところで、マルクス主義の主要なテーマであり、またユダヤ神秘主義とも通じる思想に自然の解放という考えがある。これは、自然が人間の技術によって抑圧されていると考える。そして自然の中に潜んでいる本来の可能性を救出すべきだという。パサージュに入り込むとあたかもモノがこちらを見ているという視線が感じとれる。自然の救済という思想からいえば、それはモノの中に救われないで待っているものがあるということでもある。ベンヤミンのいう遊歩者とは、単なる歩く人ではない。ブラブラ歩きまわることによって、そうしたコンステレーションを読み解き、モノを解放しようという試みだ。しかし、単純に古典的なスタイルでそれを記述したところでうまくいかないだろう。現代芸術のような新しいスタイルが必要である。そこで、ベンヤミンが試みたのが、『パサージュ論』として後に呼ばれるようになる膨大なメモによる集積だ。もはや何が書かれているのかわからないような形で記述すること。それは、見えるモノをいったん部分に分解して、まったく別のコンステレーションをつくり直す、そういうそれまで誰も試みたことのない方法でもあった」
遊歩者とは、単にブラブラとまちをほっつき歩く者ではない。都市にすでに張り巡らされているモノたちの夢、モノの背後に蠢き合っている無意識を発見する者でなくてはならない。だが、それはショーウィンドウの影に隠れている場合もあるが、白昼堂々とグラスや時計、装飾品、古書などとして表れている場合もある。いやむしろパサージュを彩るショーケースのさまざまな商品群として、それらはわれわれの眼の前にすでに放り出されているのだ。
コンステレーションを解読する。すべてが目の前にあるものから、ある関連性を見つけ出さなければならない。それは夜空にランダムに散らばって見える星々が、星座として関連づけられるのと似ている。一見バラバラに配置されているモノをある法則性、あるシステムによって関連づけ直すこと。それは演繹的方法でも帰納的方法でもない、第三の方法、C・S・パースのいうアブダクションに近い方法である。
遊歩者の独自性とはなんだろうか。それは決して観察者ではないということではなかろうか。コンステレーションを読み解くには、その世界にまず入り込んでいかなければならない。単にそれを外から眺めているだけでは、そこに張り巡らされている法則性を見つけ出すことは困難だろう。だが、だからといって完全に没入してもそれは同じように見過ごされてしまう。木を見つつ、森も見える視点。アブダクションのような中間的な立場に身を置くことによってのみ、それは可能になるのだ。遊歩者とは、その中間的な位置に身を置くことではなかろうか。
ベンヤミンが言うバロックといった状態は、穴だらけでありながら閉じている状態、この状態がまさしく中間的な立場であり、遊歩者の身体を示している。「移動」とは、バロック的な都市とバロック的な身体の相互浸透である。その様態を表現するカギ、記述するカギがコンステレーションなのである。
ビットストリーム上のツーリズム
現代の交通空間の最も典型的なものは、インターネットである。情報(コト)のパスであるインターネットは、モノ・ヒトこそ運ばないが、今や私たちの生活を支えるインフラとしてなくてはならないものに成長したといえる。昨今、次世代インターネットということがいわれるようになり、全接続状態を前提とするインターネットをベースにした新たな情報環境が議論されるようになった。そうした現代の交通空間としてのインターネットにとって、「移動」のもつ意味とは何か、メディア状況とのかかわりから桂英史氏と渡辺保史氏に議論していただいた。お二人の議論を要約してみよう。
「〈交換〉とはモノのやり取りであるが、デジタル・データになると何を交換しているのかがあいまいになる。交換というのはモノが移動することで、今回のテーマに合致する問題を孕んでいるからだ。この問題を〈知〉の交換の移動あるいはフェアユースという観点から捉えてみる。ヨーロッパ型の〈知〉のあり方が〈知〉を蓄積していくのとは対比的に、アメリカは〈知〉の利用法を重視する。蓄積よりも利用を重視する。インターネットの普及はまさにそのインフラづくりであった。しかし、情報インフラのスタンダード化が進行する過程で〈技術の理解〉が希薄になってくる。それは〈知〉の利用そのものにも影響を与える。さらにメディア環境の飛躍的な変化は、記述のノウハウをしばしば変えてしまうという。〈記述の理解〉も重要になってきている。
リナックスに代表されるコンピュータにおけるオープンソース・ソフトウェアの登場は、まさにそうした根本的なレベルでの変化を促している。それはやがて記述の体系の新しいあり方を生み出していくことになるだろう。フェアユースやオープンソースというようなモデルを考える場合重要なのは、徹底的にアノニマスになることである。アノニマスが維持されることが大きな決め手となる。
ところで、交通空間としてのインターネットを考える時、それが従来の意味での通信ではないということを知る必要がある。インターネットは通信というよりははるかに交通に近い。通信と交通の違いとは何か。景色があるかないかである。インターネットは動く景色が見える。景色が動くとツーリズムが働く。ビットストリームに乗り、次々に変化していく景色を楽しむような感覚。それはまさにインターネット独自のツーリズムの誕生だ。
一八世紀の時代にツーリズムによって他者を発見した。ウェブ上で新たなサイトを発見することは、まさしく他者の発見である。インターネットは移動の欲望にダイレクトにつながっている。移動の欲望とは、コネクトしたいという欲望のことである。プロトコルを共有することによって、まったく見ず知らずの人間と論理的につながることができるのだ」
インターネットの用語には、現実界(リアル・ワールド)の、とりわけ空間の用語が多く散見される。サイバー・スペースはもとより、サイト、マップ、ロケーション、URL〈番地〉といったように、インターネット自体が一種の巨大なランドスケープと化しているのだ(ネットスケープとかアウトルックとかインターネットのアプリケーションについても同様のことがいえる)。チャットでは、チャンネルの中に入っていく時に、二階、三階といった言葉で表現するというが、これもインターネットが一種の建築的空間としてイメージされているからにほかならない。
ネット・サーフィンなどというシャレた言い方が生まれたのも、ウェブ上のさまざまなサイトにアクセスしている場面では、確かにサーフボードに乗り波をつかまえた時の快感とそれが一致したからであろう。しかし、いまやもっと直截的に、空間そのものを移動しているという感覚を私たちはもち始めているのではないだろうか。サーフィンという言い方は、まだアクセスしている自分をどこか遠い位置から俯瞰している感じがする。しかし、「いく」「くる」「巡る」という言葉や「ネットしている」という言い方からは、自らがウェブ上を移動している感覚が滲み出ている。何が違うのか。後者ではあたかもクルマに乗って前方を見ているように、風景が手前へ手前へと次々にやってくる、あの感じがある。クルマのフロントガラス越しに見える動的な景観、速度を伴う視覚世界を、コンピュータの画面上に見いだすのである。もちろんコンピュータ・ゲームには、カーレースをはじめとしてその手のシミュレーションものはたくさんある。しかし、ここで言いたいのは、そうした仮想の現実ではない。ウェブというデジタル・メディアの風景をそのような視覚映像を見つつ移動していく、そういう感覚がすでに私たちには宿り始めているのではないかということなのだ。
「われわれは今日、高度な電子テクノロジーによってあらゆる遠近が一瞬のうちに媒介されてしまい、かつてない規模と速度で空間が消滅していくかに見える事態、およそ(空間的なもの)が(メディア的なもの)としてしか現象しなくなっているかに見える事態に直面しているからである」(「空間の政治、あるいは都市研究とメディア研究の対話をめぐって」吉見俊哉)
私たちはすでに空間の自明性を失いかけていると吉見俊哉氏は言う。代わりにメディア的なものによって再編成された空間の方を、むしろ空間として感じ始めている。デジタル・メディアの風景が私たちの風景と感受されるという転位が起こっているというわけだ。そうした感覚が身体化した時、桂氏がインターネットは独自のツーリズムを誕生させるという発言は、よりリアルなものとなるだろう。メディア上の空間の経験が、逆に現実界の空間の経験に変更を要請するような事態が訪れるかもしれない。メディアを移動する感覚が、現実の空間の移動に再参入する。そのようなデジタル・メディアと一体化した身体感覚を私たちはすでに自らのものとして感受し始めているのではないかということだ。
LETS、「移動」するメディア
西部忠氏は、「〈地域〉通貨LETS 貨幣・信用超えるメディア」で次のように述べる時、もはやLETSの意義と可能性は明らかであろう。それは資本主義経済の原プログラムそのものを変容させてしまうような対抗ガン的運動である。
「われわれは、グローバリゼーションそのものを押し止めようとしたり、それに対して背を向けて閉じ籠るべきではなく、資本のグローバル化と投機化がもたらす災禍から地域経済を防御しながら、内生的・自律的な成長を遂げる道を模索すべきであろう。言い換えると、遠心的なグローバリゼーションと求心的なローカリゼーションを拮抗させうるような制度設計を意識的に求めつつ、それを自発的に構築する方向を模索すべきである。それは、中央集権型計画経済におけるようなグローバルな設計主義ではなく、分散型市場を内包するようなローカルな設計主義に依拠するものだ。
グローバリゼーションとローカリゼーションという二つの相反する動きが自生的に融合していくような複雑なシステム進化へ向かう動きを〈グローカリゼーション〉(Glocalization)と呼ぶならば、LETSとはそうした指向性をもつ一つの運動形態である。LETSは、〈グローバリゼーション〉という名の妖怪を退治するグローバルかつローカルな〈ゴーストバスターズ〉として登場してきたのである」
LETSとは何か、もう一度簡単に整理しておこう。 LETSは参加者が財・サービスを自発的に取引しあう自律的な経済ネットワークであり、各参加者が交換媒体として固有の地域通貨を発行・管理しながら利用するしくみである。
LETSは、「同意」「無利子」「共有」「情報公開」の四つの原則からなり、次のような特徴をもつ。 一、流通圏が限定されている地域通貨である。二、無利子である。三、信用創造を基本的には行わない。四、多主体による分散的発行貨幣。五、信頼を基本とする。六、貨幣保有動機の多面化。七、「経済メディア」を超えて「文化メディア」になる可能性をもつ。
この中で、西部氏がとくに関心をもつのが最後の「文化メディア」の可能性である。経済的な取り引きを目的とする貨幣が、価値や文化をアピールするものへと発達していく可能性をもっているというのだ。なぜそのようなことが可能になるのか。それは、LETSの特徴に挙げた中にある多主体による分散的発行貨幣、無利子、地域通貨であるといった、貨幣が貨幣として立脚していた部分をみな捨ててしまうからである。そのことによって、純粋な経済メディアとしての性質を失い、それがかえって文化的メディアへと変貌していくきっかけを生むのである。そうなるともはや物理的な地域にしばられていることもなくなってくる。価値観を共有するような、自生的なネットワークとして地域の概念を拡張していくことも可能になると西部氏は言う。
LETSには、もう一つ重要な側面がある。LETSを考えることが端的に市場というものを問い直し、その可能性を広げていくことにつながるというのである。LETSは、市場経済と似ているが若干異なるところがある。しかし、その微妙な差異がシステム全体の作動性を大きく変える可能性をもっている。それは市場経済の全面的な変更や新たな経済システムを再構築するような設計主義の問題を回避しながら、なお経済社会を変える可能性を指示している。LETSは市場経済の中に微細な差異や多くの異物を差し挟んでいくことで、それらの存立構造の基盤そのものを揺るがすものになるという。
LETSには、これまでの生産主導の経済論理から、流通を主軸に置いた経済論理へ転換する契機が潜んでいる。「移動」という言葉で言い換えれば、資本の「移動」に対抗する流通それ自体の「移動」を構想することができるだろうというのである。ここでいう「移動」は、経済的な領域から文化的な領域への「移動」や閉じた個や企業から、開いた多重人格的な個や企業への「移動」といったように、多義的な意味を有している。LETS
が、このように多義的で多面的な「移動」を可能にするメディアとなる時、モノ・カネ・ヒトの移動からなることが自明とされてきた経済活動自体を問い直すことになるかもしれない。
「行為」を記述する
アフォーダンス理論は、一般的に「環境の中に実在する情報を探し出す」行為というように説明されてきた。つまり、アフォード(afford)「〜ができる、〜を与える」からつくられた造語という成り立ちから、知覚者と環境とのインタラクションによって得られる情報がアフォーダンスだという理解である。しかし、この説明は不十分である。環境にたくさんの情報が埋め込まれているというところはいいとしても、それを環境に探し出す知覚者が、この説明ではアプリオリなものとして存在していることになる。つまり、これでは環境から価値ある情報をピックアップするのは、最終的には知覚者の主観だということになってしまう。知覚者が環境から情報を得る行為がアフォーダンスだという説明は、結局のところ旧来の知覚心理学の図式を踏襲するものである。
ギブソンのねらいは、まさにそうした旧来の知覚心理学の図式から抜け出すことにあった。それは、簡単に言えばこの図式から知覚者の主観を追い出すことである。アフォーダンスの考えの根本にあるのは、それが知覚者の主観によるものではないということだ。生態心理学の革新的な意味を一つ挙げるならば、心理学にとって自明とされてきた主観をとりあえずかっこに入れて、実在するものだけを問題にしようとした点にある。もとより知覚者は、その場面では主体として実在する(ただ、ギブソンの著書を精確に読み込んでいくと、主体の存在も危うくなるが、ここでは混乱を防ぐためにその議論はしない)。そしてその方法論を練り上げていくプロセスにおいて、光学から多くのヒントを得ていることである。生態心理学と光学の関係、「移動」を記述する方法を考察するうえで、生態心理学が有益だと考えるのは、まさにこの光学の理論が参考になるからである。
理解を補うために、環境についてのギブソンの定義を紹介しておこう。 「environmentという用語を使用するとき、それは、知覚し、行動する生活体、すなわち動物の周囲の世界を差している」
「環境の本質は、それが個体を取り囲んでいる(surround)ことである。〈…〉一つの物理的対象が、物理的世界のその他のすべての物理的対象によって取り囲まれている状態、すなわち物が物によって取り囲まれている状態と、生きている動物が環境に取り込まれている状態とはまったく異なる」(いずれも『生態学的視覚論』)
環境は、動物の周囲の世界である。ギブソンは、生きて動く動物を取り囲むものが環境であると定義する。つまり、動物のいないところは、環境とは考えていないのである。このことをまず押さえておく必要がある。
三嶋博之氏のインタビューを要約してみよう。 「〈移動〉は、生態心理学でいう〈探索〉を含む概念である。それは正解自体を探索することである。そのプロセスでカギとなるのは、知覚と行為の循環のプロセスである。
太陽から来た光は大気や地面などに反射し、その結果地上ではあらゆる方向から光が入ってくる。これが〈照明〉だ。また、地面にはいろいろなものがあり、それによって光はいろいろな角度に反射したり吸収されたりする。そういう光のムラがパターンとしての人に向かってくる。これを包囲光という。私たちはこの光のパターンを利用することで外界を認識している。
この光のパターンというのは生物が存在する前からあったが、生物はこの光のパターンを識別し、利用できるように進化していった。目はそのプロセスで生まれた。植物にとって光はエネルギーである。動物は光合成ができないが、人間の目はその名残ではないかと考えることができる。
人間はこの光のパターンをどのように利用しているのだろうか。たとえば「移動」することによって、光のパターンは変化する。手前のものほど大きく速く、遠くのものほど遅く少ない。その動きの違いによって、奥行き感が得られる。私たちは常に、光のパターンが生まれるところに向かって進む。パターンの変化は、その人の進行方向を特定し、また人が動けば光のパターンも動く。人と光のパターンは相互に循環する。
物理学においてモノが互いに影響し合う場合は、ぶつかったり、あるいは磁場のように必ず力のやり取りが絡んでくる。これをハイエナジーカップリングという。それに対して知覚には、今言った人と光のパターンの関係のような力を介さない伝達のシステムがある。これをローエナジーカップリングという。生物は物理学の領域を超えたところで、情報と力のカップリングを行っていると考えられる。
脳は知覚と行為のカップリングにかかわっている。ただし脳がなくても、接続すればインタラクションする。事実ミミズやシロアリも知覚と行為のカップリングができる。人間は複雑な脳をもっているので別の使い方をしているだけだ。このように考えると、モノから人間までを連続的に眺めることができる。
ところで、オーダーパラメータ(マクロ)の変化を駆動するような変数が、コントロールパラメータ( ミクロ)である。生物の世界では、オーダーパラメータがコントロールパラメータになるということがしばしば起こる。新たに出てきた秩序が、逆にシステムの秩序自体を変えてしまう。
一般にいわれる自己組織化は、たとえば、脳のようにミクロ↓マクロという方向だが、マクロ↓ミクロという方向も出てくる。それが知覚というシステムの特徴である。マクロのパターンがミクロにどう還流するのか。たとえば、からだの筋肉の細胞を活性化させてからだの動きを形づくる。つまりミクロからマクロが立ち上がる。それが結果的にマクロな空間とマクロなからだの動きがフィットする。そういうふるまいとして知覚のマクロを見る。ミクロとマクロだけではなくて、知覚のマクロを見ることもできるのだ。
知覚には終わりはないというのが一つの結論である。視覚的な探索。移動は、同じところを通っても一回一回見ているところが違う。それをどう記述するかである。 ギブソンには公共性という概念がある。これは、自分があらゆる場所に同時にいる可能性も含んで、今自分が見えているものがあるというように解釈することができる。あらゆる場所に同時にいるということは、違う場所に他人がいるということも含んでいる。この知覚の公共性、知覚の可能性をファインマンの経路積分の方法を使って個人の運動につなごうという考えがある。これは、いうなれば量子力学の記述方法を応用しようというものだ。
記述には、単位が重要だが、記述の単位はその課題によって変わる。先に単位を決めることはできない。 周期のない一回限りの行為でも、一振りしかしない振り子時計だと考えれば、周期的な運動として記述できる。つまり一振りしかしないような時計を一回一回つくる。それが生物の〈行為〉である。その時計の単位を探し分析することで〈記述〉することができるかもしれない」
光はエネルギーである。私たち人間は植物の光合成のように、それをエネルギーとして利用することができない。だが、それを別の仕方で利用している。包囲光という概念によって、私たち人間が光をどう利用しているか、また、それがどれだけ重要な働きをしているかについて、徹底的に分析したのがギブソンであった。彼は、それを生物と環境の関係、生物進化の過程と擦り合わせながら考えていった。生態学心理学はその意味で生態学的光学であり、アフォーダンス理論は、生態学的光学との連関で押さえておかないと、先に言ったような誤解を生ずることになる。
さて、「移動」の記述法を探るにあたって、三嶋氏が述べた人と光のパターンの相互循環は、重要なポイントとなると思われるので、そのことについて指摘しておきたい。私たちは、常に光のパターンが生まれるところに向かって進むという。この指摘は、私たちがどのように光を利用しているかを端的に示しているが、それよりも、この論理機序に生態心理学の特異性が表れているように思う。私たちの知っている視覚の理論は、目がどのようにして外界を見ているかというしくみを説明するものであった。必ずそれは、目をレンズと見立てて、外の景色がレンズを通して網膜に到達し像をつくるという図式であった。そして、網膜に写し出された像は必ず逆立ちをしている。私たちは、この図式を自明のものと思い続けてきたのである。
しかし、果たしてこれで視覚のしくみが本当に説明されたことになるのだろうか。『談』no.54「唯〈脳-身〉論」のeditor's note で、脳の情報処理機構を説明するにあたってホムンクルスの図があることを指摘したが、この視覚を説明する図式は、このホムンクルスの図を踏襲しているのである。つまり、ホムンクルスの図は情報処理機構のメカニズムを図示するものだが、そこでやり取りされている情報については棚上げにされたままである。同様に、視覚の理論を説明するこの図式において、外界がレンズを通して網膜に像をつくるという関係はわかるが、それがなぜ見ることを説明することになるかについては棚上げにされているのである。つまり、なぜ見えるのかという疑問については、この図式は答えを出していないのだ。問題はそれだけではない。じつはこの図式自体が視覚の理論とはいいにくいものなのである。
ギブソンは、明確にそのことについて述べている。私たちは、物理的エネルギーとしての光と、視覚に対する刺激としての光と、知覚情報としての光を混同しているというのだ。要するに、このレンズの比喩は、あくまでも物理的エネルギーとしての光のしくみを説明するもので、視覚に対する刺激としての光の説明ではない。ましてや、知覚情報の光を考えるには、かえって邪魔になる図式なのだ。ギブソンはこの議論を緻密に行っているので、詳しくはギブソンの著書を参考にしていただきたい。ここで一つだけ指摘するとすれば、ここにある混乱は、その知覚していると思われる現象をどの位置から見ているかということである。つまり、どこからの眺めなのかということだ。
桂氏と渡辺氏の対談の要約の際にも触れたことだが、私たちが見ているという知覚は、私の外にはない。私の知覚は、私の中にある。私が見ているのが、私の「見え」なのであり、それ以外の「見え」はない。知覚・行為の記述は、この前提から始まる。そして、私たちが問題とする「移動」の記述も、ここからしか始まらないのだ。
三嶋氏の議論は、そのまま最後の河本英夫氏の議論へとつながっていく。
「移動」の記述法、それは「差異」を経験科学に接続することだ
二つの木を強く擦りつけると、やがて摩擦で火が起きる。火のつく瞬間の場面を知覚することはできるが、摩擦運動が火に転換するその一瞬の変化そのものを知覚することはできないと河本英夫氏は言う。私たちは、そんなことさえまだできないでいるというのである。これは知覚の側の問題だが、それを記述する方法においても同様のもどかしさがある。editor's
note beforeでも紹介した細胞とアニメーションの比喩だ。細胞の動きを記述しようとする場合に、アニメーションのような記述法を使うことはできない。あれだけ自明な細胞の動き一つですら、われわれはいまだにきちんとした形で記述することができていない。つまり、私たちは知覚の領域においても、それを記述し伝える表現・伝達の領域においても、足踏みを続けているのである。なぜそのような足踏み状態を強いられているのだろうか。それは、単純化すればそうした事態を私たちが経験科学にまだうまく接続することができないという事情によるものだ。
河本氏の発言に沿いながら、その事情を考えてみよう。 まず、私たちは「変化」というものをうまくつかまえることができていないという。 「中間物がなく、隔絶しているような異なるものの〈質〉の変化を、メタモルフォーゼと呼んでいる」
精神医学では分裂病という症状がある(とされている)。精神というものは経験の主体であるが、精神にはあらかじめ定まった境界も、形も、作動の様態ももたないものだ。それゆえ精神と呼ぶほかないものだが、だから精神が分裂するという考えはそもそも矛盾しているのである。河本氏の考えを敷衍すれば、精神はただメタモルフォーゼするだけにすぎない。精神疾患とは、このメタモルフォーゼを指している。
「〈質〉の変化の基本は、退路を断つこと。身体行為における変化は、すべて退路を断つという変化である 」 河本氏が、自転車乗りの例を出して説明されたのがこの退路を断つという変化である。河本氏の言うように、身体の特徴の一つであるこの退路を断つということは、自転車に乗ることも含めて日々生活する全域で始終起こっていることである。たとえば、最近新しく学習したことなどを考えてみるとわかりやすい。ケイタイの使い方や電子メールの使い方、またキーボードの打ち方でもいい。こうしていったん新しく覚えたスキルは、簡単には忘れてしまうことができない。それが簡単であればあるほど、忘れることは困難になる。それが退路を断つということだ。もっと典型的な例を紹介しよう。言語のことだ。日本人である自分が、日本語を外国語のようにもう一度一から覚え直すということはできない。それを忘却することさえ難しい。
コンピュータは、初期化してハードディスクを入れ替えるということが容易にできる。しかし私たちは、それができないのである。それが身体の大きな特徴なのだ。つまり、私たちの身体は、後戻りということができないしくみになっている。前へ前へと行くしかない。それがすなわち「生きている」という事態であることは、もはやいうまでもないことだ。
「それ自体で動いているものは、直観的には理解できるが、それを記述しようとすると困難をきわめる。そのことはベルグソンが繰り返し指摘したことだが、現代ではドゥルーズがこの問題にアプローチしている。ドゥルーズは動きという言い方をやめて差異化という概念で捉え直そうとした。自らが自らを差異化する。その差異化の繰り返しとして動きという事態をつかまえようとしたのだ。運動あるいは移動を差異化として考えるというのがドゥルーズのねらいであった」
ドゥルーズが繰り返し述べていた差異化とは、自己が自己を差異化していくことである。それは退路を断つことと同じことを示している。したがって、ただ差異化し続けていくことが私たちの身体のあり方だということになる。しかし、これを記述することは難しい。
変化のカテゴリーにはもう一つ「起滅」があるという。突然消滅し、逆に今まで何もなかったところに、突然何の前触れなしにポカッと現れること。これが「起滅」であるという。これはとっぴなことのように思われるが、たとえば平衡系ならどこでも起こっている「ゆらぎ」は一種の起滅と考えられるだろうと、河本氏は言う。ただ、これも記述の段階で困難をきわめることになる。現状では、「ゆらぎ」という形でしかつかまえられないし、それがどこに起こるか予測すらできないからである。
さらにもう一つやっかいなものがある。 「たとえばある場所で加速しながら二〇キロで通過するクルマと、減速しながら二〇キロで通過するクルマとでは、その瞬間の速度が同じでも明らかに雰囲気や気配が異なる。時間、空間で表記される対象以外の雰囲気や気配で、しかも変化していると感じ取れるもの、それが強度である」
「近代科学の量化傾向の中で、量化しきれないものを表す概念として強度がある。中世スコラの時代にドゥンス・スコトゥスが言ったもので、同じ大きさの火でも火の強さが異なる場合に、この強さの度合いを表すために用いたものだ。強度・内包量の概念は、測定ができないわけで、当然近代科学では扱いづらい」
これも変化のカテゴリーに含まれるものであるが、同様にそれを記述することは難しい。なぜならば、それはいわば知覚の余剰としてあるからだ。雰囲気や気配としかいえないようなもの。だが、まちがいなく感じ取れるもの。知覚の余剰、すなわち知覚の方が張り出しているのである。
では、どうしてそうした事態を記述することが困難なのだろうか。河本氏は、その原因の一つに、感覚の経験の回路と言語的回路の分断があるからだという。つまり、二つの回路が別個に独立してあるからだというのだ。
「言葉は言葉でネットワークをつくり、イメージはイメージでネットワークをつくっている」 しかしそれは、まったく孤立しているわけではなく、いやそれどころか互いに接近したり、重なり合ったりしているという。
「異なるネットワーク間がつながっていることを、浸透(penetration)と呼ぶ。浸透は、因果関係でも作用/反作用という関係でもない。もちろん意味論的な関係でもない。移動を考える時に最も重要なカテゴリーとなる」
たとえば色について考えてみよう。色の感覚知覚は、三五○○○種程度区別されるといわれているが、言語的に区別できるのはせいぜい五○種以下である。感覚は言語と重なり合わない。だが、そう知ったところで、感覚している五○種以上の色を切り捨てることは感覚の中では不可能ではないか。私たちがすでに感覚しているものを、忘却し捨てることはきわめて難しいことである。まさにここでは感覚が張り出しているのである。その時に感じるのは、あのもどかしさであろう。
河本氏は、そこで次のような戦略をたてる。 「今ここで問われているのは記述の系そのものが変化していくような記述の系のことである。つまり、表現が変わっていけば記述の系がどんどん変化していく、そういう系がつくれないかということだ」
そしてその一つの方法論として提起するのが、オートポイエーシスである。 「オートポイエーシスは哲学や思想ではなくシステム論であり、経験科学である」 オートポイエーシスの大きな特徴は、「それが要素の集合から定義するのではなく、作動の継続から要素の集合がそのつど決まっていくとした点にある」〈『オートポイエーシス2001』〉という。
「オートポイエーシスは生成プロセスのネットワークであるということが重要である。システムというのはそれを構成する構成要素の集合ではないということである。生成プロセスのネットワークというのは、連続的に動いている。システムは構成素を産出し、その構成素のうちシステムをさらに作動させるものが生じる。ここにシステムと構成素の間の循環が生じる。フィードフォワードになっているわけだ。このフィードフォワードによって区切られるものがシステムの自己(Sich)である。この自己(Sich)には、あらかじめ定められた境界、つまり確定した境界がない。システムは要素を産出し、そのうちシステムを作動させるものがシステムの構成素となるだけだからだ。この自己(Sich)の連続的産出は、まさしく生きていることの別名である」
自己の連続的産出、それが行為である。そして私たちが問題にし続けてきた「移動」は、この行為のことであった。それはまた、際限のない差異化の繰り返しでもある。差異が自らを生み出していく系として、自らを見ていくこと。「移動」はその典型的なあり方なのである。
三嶋氏が最後に述べたことは、ここでオートポイエーシスに接続されることになる。差異化し続ける自己、日々新たに生まれ変わっていく自己とは、あらゆる場所に同時にいることの可能性を示唆するからである。自己は一個の個体でありながら、同時にあらゆる場所にいることが可能な、そういう様態をもつものなのだ。
「移動」について考えることは、何を問題にすることなのだろうか。その問いに対して、オートポイエーシスは次のように答える。 「走る自分にとっては、内も外もない。自分が走ることで円ができる。自分の走りが自己の境界を区切る、ただそれだけだ。もしも自分が走るのをやめれば、円もその時点で消滅するし、また再び走り始めれば円ができる。こういう感覚を経験科学の領域にどうやって接合することができるのか、まさにそれがわれわれの課題なのである」
そこにあるのは循環であり、差異化である。私たちの感覚の、そして思考の原点にあるものである。
| | |